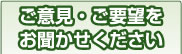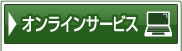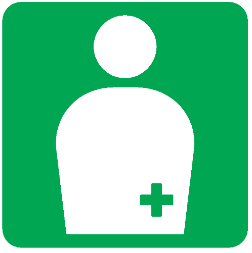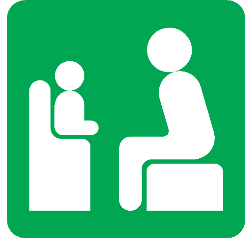ここから本文です。
更新日:2025年4月1日
国民健康保険税に関すること
納税義務者
下松市の国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主です。
税額の計算方法
保険税額について(令和7年度税額)
国民健康保険税は、基礎課税額(医療分)、後期高齢者支援金等課税額(支援金分)および介護納付金課税額(介護分)の合算額です。
| 医療分 (限度額660,000円) |
所得割額 | 算定基準額×税率7.3%(各被保険者ごとに算定) |
| 均等割額 | 1人当たり23,000円 | |
| 平等割額 | 1世帯当たり20,000円 | |
| 支援金分 (限度額260,000円) |
所得割額 | 算定基準額×税率2.7%(各被保険者ごとに算定) |
| 均等割額 | 1人当たり7,500円 | |
| 平等割額 | 1世帯当たり7,500円 | |
| 介護分 (限度額170,000円) |
所得割額 | 算定基準額×税率2.7%(第2号被保険者ごとに算定) |
| 均等割額 | 1人当たり8,900円 | |
| 平等割額 | 1世帯当たり6,000円 |
算定基準額は総所得金額の合計額から430,000円を控除して算出します。(合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額によって控除額が逓減します。)
所得割額、均等割額は被保険者のみ算定します。被保険者でない世帯員は含まれません。
介護分は40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者のみ課税されます。
年度途中の加入、脱退の世帯については、加入月数で保険税額を計算します。
均等割額、平等割額の軽減制度について
世帯主及び被保険者の総所得金額等が以下の要件に該当する場合、均等割額と平等割額の合計額をそれぞれ7割、5割、2割を軽減します。
軽減制度を受けるには申請の必要はありませんが、所得の申告をしておく必要があります。世帯の中に一人でも未申告者がいると軽減を受けることはできませんので、収入がない方でも住民税の申告は必ずしてください。
430,000円+〔(給与所得者等の数※1-1)×100,000円〕以下のとき・・・7割軽減
|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|
|---|---|---|---|
|
均等割額1人当たり |
23,000円→6,900円 |
7,500円→2,250円 |
8,900円→2,670円 |
|
平等割額 |
20,000円→6,000円 |
7,500円→2,250円 |
6,000円→1,800円 |
430,000円+〔(給与所得者等の数※1-1)×100,000円〕+〔305,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数※2)〕以下のとき・・・5割軽減
|
|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|---|---|---|---|
|
均等割額1人当たり |
23,000円→11,500円 |
7,500円→3,750円 |
8,900円→4,450円 |
|
平等割額 |
20,000円→10,000円 |
7,500円→3,750円 |
6,000円→3,000円 |
430,000円+〔(給与所得者等の数※1-1)×100,000円〕+〔560,000円×(被保険者数+旧国保被保険者数※2)〕以下のとき・・・2割軽減
|
|
医療分 |
支援金分 |
介護分 |
|---|---|---|---|
|
均等割額1人当たり |
23,000円→18,400円 |
7,500円→6,000円 |
8,900円→7,120円 |
|
平等割額 |
20,000円→16,000円 |
7,500円→6,000円 |
6,000円→4,800円 |
軽減判定をする所得は「専従者控除」や「分離譲渡所得等の特別控除」の適用前の金額です。
なお、65歳以上の方の公的年金等に係る雑所得については、150,000円(所得額が150,000以下の場合は、その額。)の控除があります。
1 「給与所得者等の数」とは、一定の給与所得者(給与収入が550,000円を超える方)と公的年金所得者(公的年金等の収入が600,000円を超える65歳未満の方、または公的年金等の収入が1,250,000円を超える65歳以上の方)をいいます。
2 「旧国保被保険者」とは、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得した日において、国民健康保険の被保険者の資格を有し、かつ同一の世帯に属する国民健康保険の世帯主(以後継続して世帯主である方に限る。)と当該日以後継続して同一の世帯に属する方(当該日に国民健康保険の世帯主であった場合は、当該日以後継続して国民健康保険の世帯主である方)のことをいいます。
子どもに係る均等割の軽減措置
未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者)の医療分と支援金分の均等割の5割を減額します。
なお、上記の軽減に該当する世帯の未就学児については、当該軽減後の均等割の5割を減額します。
産前産後期間の国民健康保険税の減額について
子育て世帯の負担軽減や次世代育成支援の観点から、出産する予定がある国民健康保険の被保険者または出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税が減額される制度です。
【対象者】
下松市国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に出産する(した)方
出産とは、妊娠85日(4か月)以上の分娩をいいます。
(死産、流産、早産および人工妊娠中絶をされた方も含みます。)
【対象保険税】
令和6年1月以降、対象者の減額対象期間における所得割額と均等割額
【対象期間】
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間
| 3か月前 | 2か月前 | 1か月前 |
出産 予定月 |
1か月後 | 2か月後 | 3か月後 | |
|
単胎 の方 |
― | ― | 対象期間 | ― | |||
|
多胎 の方 |
対象期間 | ― | |||||
【申請方法】
(1)本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証など)
別世帯の方が申請される場合は、世帯主からの委任状が必要になります。
(2)母子健康手帳など
出産後に子が別世帯にいる場合、出産日および親子関係を明らかにする書類が必要になります。
上記のものを添えて、市保険年金課国民健康保険係(市役所8番窓口)に申請してください。
届出書は窓口に備え付けています。出産予定日の6か月前から届出ができます。
離職(倒産・解雇・雇い止めなど)された人へ
平成22年4月から国民健康保険税が軽減される場合があります。
【対象者】
次の項目にすべて当てはまる人
(1)平成21年3月31日以降に離職され、離職時に65歳未満だった人
(2)雇用保険の特定受給資格者(倒産・解雇などによる離職)又は特定理由離職者(雇い止めなどによる離職)
雇用保険受給資格者証の第1面「離職年月日理由」欄の理由コードが11・12・21・22・31・32(特定受給資格者に該当)と23・33・34(特定理由離職者に該当)のいずれかの表示になっている人が対象です。
【軽減額】
国民健康保険税の前年所得に対する税額について、前年の給与所得をその30/100とみなして算定
離職した人のみ適用
給与所得以外は100/100として算定
(例)前年の給与額が300万円(所得に換算すると202万円)の場合
今年度の課税額は、2,020,000円×30/100=606,000円を基に算出します。
【軽減期間】
離職日の翌日から翌年度末までの期間
国民健康保険加入中は、就職しても引き続き軽減が継続しますが、国民健康保険を脱退すると、軽減は終了します。
(例)令和7年4月1日に解雇により離職した場合
軽減対象期間は令和7年4月2日~令和9年3月31日
【申請方法】
雇用保険受給資格者証(写し可)を添えて、市保険年金課国民健康保険係(市役所8番窓口)に申請してください。
特例受給資格者証(季節的に雇用される方又は短期雇用特例被保険者の方が所有)、高年齢受給資格者証をお持ちの方は対象となりませんのでご注意ください。
後期高齢者医療制度の創設に伴う軽減措置について
国民健康保険から75歳以上の人など後期高齢者医療制度に移行する人を含む世帯の場合(申請の必要はありません)
75歳以上の人などが後期高齢者医療制度に移行することに伴い、その世帯の国民健康保険税が急激に増えることがないように、軽減措置を講じます。
ただし、後期高齢者医療制度に移行した旧国保被保険者がその世帯から異動した場合、世帯主が変更された場合はこの措置は受けられなくなりますのでご注意ください。
1.所得が少ない世帯に対する軽減について
国民健康保険税で軽減を受けていた世帯について、世帯員が後期高齢者医療制度に移行したことにより、世帯の国民健康保険被保険者が減少しても、同じ軽減措置が受けられるよう、移行した被保険者を含めて軽減の判定を行います(ただし、世帯の構成や収入が変わった場合は、再度、軽減措置の適用を判定します)。
2.世帯ごとに負担する平等割額の軽減について
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度へ移行したことにより、同じ世帯の国民健康保険加入者が1人となった世帯を「特定世帯」といいます。
特定世帯は、5年間、医療分と支援金分にかかる平等割が2分の1軽減になります。
5年経過後は、3年間「特定継続世帯」として、平等割額が4分の1軽減になります。
この軽減適用は、国民健康保険被保険者が1人で、後期高齢者医療制度へ移行した人と継続して同じ世帯である場合です。
社会保険などの被保険者が後期高齢者医療制度に移行したため、その被扶養者(65歳~74歳に限る)が新たに国民健康保険に加入することとなった場合(申請が必要です)
社会保険などの被保険者本人が後期高齢者医療制度に移行した結果、国民健康保険に加入することとなった65~74歳の被扶養者(旧被扶養者)は、申請により当面の間、以下の措置が受けられます。(下記2.及び3.については、加入日から2年間のみ実施。)
- 旧被扶養者に係る所得割が賦課されません。
- 旧被扶養者に係る均等割が半額になります(7割または5割軽減に該当する世帯を除く)。
- 旧被扶養者のみの世帯は、平等割が半額になります(7割または5割軽減に該当する世帯を除く)。
特別徴収について
平成20年4月からの医療制度改革に伴い、65歳から74歳の国民健康保険の加入者で一定の条件を満たす世帯主の方については、平成20年4月から国民健康保険税を年金からあらかじめ引かせていただくこと(特別徴収)となりました。
特別徴収の対象となる方
次の1.~4.すべてに該当する方は、原則として年金からの特別徴収となります。
- 世帯内の国民健康保険の被保険者が全員65歳以上75歳未満であること
- 世帯主の年金が年額18万円以上であること
- 世帯主の介護保険料が年金からの特別徴収となっていること
- 世帯主の介護保険料と国民健康保険税の合計額が年金受給額の2分の1を超えないこと
特別徴収の時期
年金からの特別徴収は、年金支給月(4月、6月、8月、10月、12月、2月)の年6回です。
特別徴収税額の決め方
最初の3回(4月・6月・8月)は仮徴収期間、残りの3回(10月・12月・2月)は本徴収期間といい、1回あたりの特別徴収税額は、それぞれ次のとおりとなります。
|
仮徴収税額 (4月、6月、8月) |
《前年度が特別徴収であった場合》 |
|---|---|
|
本徴収税額 (10月、12月、2月) |
当該年度の確定年税額と仮徴収税額の差額分を3分の1にした額 |
口座振替への変更について
公的年金からの特別徴収の対象者となる方は、申出書を提出することにより、口座振替へ支払方法を変更することができます。
お問い合わせ